新規事業を「外注」し始める大企業。 そのとき若手よ、君は何を学ぶか? - 元外資系人材開発担当が語る、Google社を参考にした、これからの時代の生存戦略 -
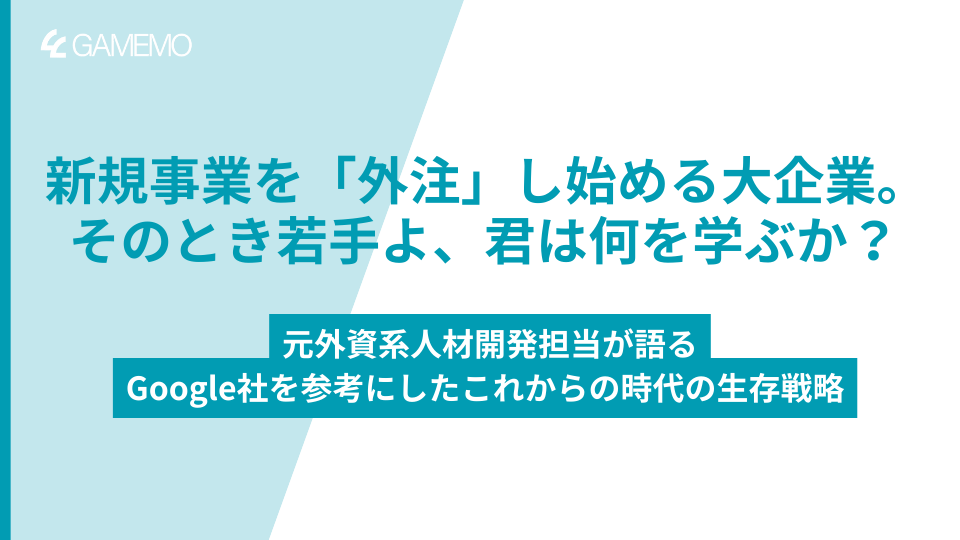
外資系企業文化やGoogleの成功事例を踏まえ、日本の大企業が新規事業を外部委託する必然性と、その現場で若手が学ぶべき7つのスキルを解説。変化の時代を生き抜くための実践的ビジネス生存戦略を提示します。
コンテンツ [表示]
- 1第1部 なぜ日本の大企業は「自前」でイノベーションを起こせないのか? - 外部委託という必然の選択 -
- 1.1心理的安全性の欠如が「挑戦の種」を枯らす
- 1.2「プロダクトアウトの呪縛」と顧客不在の開発
- 1.3「サイロ化」という名の見えない壁
- 2第2部 アウトソーシング時代の「羅針盤」- 若手よ、君たちは何を学ぶべきか? -
- 2.11. 「課題発見力」- "Why"を深く問う力
- 2.22. 「越境するコミュニケーション力」- 翻訳家であれ
- 2.33. 「高速仮説検証(リーン)力」- 小さく、賢く失敗する勇気
- 2.44. 「PLを読む力」- ビジネスという"共通言語"の習得
- 2.55. 「専門性の"タグ"」- "T型人材"を超え、"π型人材"へ
- 2.66. 「外部ネットワーク構築力」- 社外に"師"と"仲間"を持つ
- 2.77. 「アンラーニング(学びほぐし)力」- 昨日の成功体験を捨てる勇気
- 3第3部 君たちは未来の「事業家」だ - 外資系企業が求める人材と日本企業の可能性 -
- 3.1Google社が求める「スマート・クリエイティブ」との合致
- 3.2アウトソーシング時代を「最高の学びの場」に変える
- 3.3未来は、君たちの手の中にある
第1部 なぜ日本の大企業は「自前」でイノベーションを起こせないのか? - 外部委託という必然の選択 -
皆さん、こんにちは。私はかつて外資系企業で人材開発や組織改革に携わり、現在は多くの日本企業を支援しています。
最近、私が非常に興味深く見ている現象があります。
それは、日本の名だたる大企業が、社運を賭けたはずの「新規事業開発」を、外部のコンサルティングファームや専門家集団に次々とアウトソーシングしている、という現実です。
一見すると、これは奇妙な光景に映るかもしれません。
「自社の未来を創る最も重要な仕事を、なぜ外部に委ねるのか?」と。
しかし、私はこの流れを、日本企業が次のステージへ進むために避けては通れない、合理的で「必然の選択」だと捉えています。
この奇妙な現実の奥には、日本の大企業が抱える根深い構造的問題が横たわっているのです。
心理的安全性の欠如が「挑戦の種」を枯らす
私がいた外資系企業で何よりも大切にしてきた文化、それはGoogle社でも話題となった「心理的安全性(Psychological Safety)」です。
チームの誰もが、リスクを取ることを恐れず、自分の意見やアイデアを安心して発言できる環境。これこそがイノベーションの土壌です。
そこでは、壮大に失敗したプロジェクトのリーダーが、非難されるどころか「よく挑戦した」と称賛され、次の重要なプロジェクトを任されることすらあります。
失敗は、学習の機会であり、データなのです。
翻って、日本の多くの大企業はどうでしょうか。
いまだに根強い減点主義の人事評価。
一度の失敗がキャリアの汚点となり、挑戦する者より、何もしない者が評価される。
このような環境で、誰がリスクを冒してまで前例のない新規事業に身を投じるでしょうか? 心理的安全性のない組織では、社員は自らを守るために挑戦の種を心の中にしまい込み、結果として組織全体が緩やかに衰退していく。
これが現実ではないでしょうか。
「プロダクトアウトの呪縛」と顧客不在の開発
日本の企業は、素晴らしい技術を持っています。
その品質と緻密さは世界に誇るべきものです。
しかし、それが時として「良いものを作れば必ず売れる」という「プロダクトアウトの呪縛」に繋がってしまいます。
技術者が主導権を握り、顧客の真の課題やニーズを深く探求することなく、最高のスペックを搭載した「自己満足のプロダクト」を開発してしまう。
皆さんも、ご存じ検索で有名なGoogle社の有名な言葉に「ユーザーにフォーカスすれば、他のことはみな後からついてくる」というものがあります。
どんなに優れた技術も、それがユーザーの課題を解決しない限り、ビジネスとしての価値はゼロです。
新規事業とは、技術を披露する場ではなく、顧客のペイン(痛み)を解消し、その対価として収益を得る活動なのです。
この顧客中心という最も基本的な原則が、組織の論理の中で忘れ去られてしまうのです。
「サイロ化」という名の見えない壁
そして、最大の問題が、部門間の断絶、いわゆる「サイロ化」です。
営業、開発、マーケティング、管理部門。それぞれが自部署の目標達成を最優先し、見えない壁を築いている。
新規事業は、これらすべての部門を横断する総合芸術です。
しかし、日本の大企業でそれをやろうとすると、部門間の利害調整や稟議、根回しといった、膨大で非生産的な「調整コスト」が発生します。
意思決定は遅々として進まず、市場のスピード感から完全に取り残されていく。
私が知る外資系企業のエンジニアは、プロジェクトの初期段階からマーケターや法務担当者と直接対話し、フラットな関係で議論を戦わせます。
オープンなコミュニケーションこそが、スピードと質の高い意思決定を生むのです。
これら「心理的安全性の欠失」「プロダクトアウトの呪縛」「サイロ化」という三重苦を抱える組織が、自前でスピーディーに新規事業を成功させるのは、残念ながら極めて困難です。
だからこそ、企業は外部のプロフェッショナルに頼るのです。
彼らは社内のしがらみや政治力学とは無縁です。
忖度なく「そのアイデアは顧客不在ですよ」と"No"を突きつけ、過去の成功と失敗の経験則から、最短距離で市場の反応を確かめにいく。
固定費として人件費を抱えるのではなく、プロジェクト単位で変動費として外部の専門性を「買う」。
これは、現在の日本企業が置かれた状況を考えれば、極めて合理的な経営判断なのです。
第2部 アウトソーシング時代の「羅針盤」- 若手よ、君たちは何を学ぶべきか? -
さて、ここからが本題です。
この「新規事業のアウトソーシング化」という大きな潮流を、若手の皆さんはどう捉えるべきでしょうか。
「自分たちの成長の機会が奪われる」と悲観的になる必要は全くありません。むしろ、これは皆さんにとって、これ以上ない「最高の学びの機会」なのです。
会社が用意したキャリアパスに乗り、定年まで安泰という時代は、もう終わりました。これからは、会社というプラットフォームを活用しながら、自らの市場価値を高め、どこでも通用するプロフェッショナルを目指す「ギグワーカー的マインドセット」が不可欠です。
外部のプロフェッショナルと共に働く日常は、そのための最高のトレーニングジムなのです。
では、具体的に何を学ぶべきか。私が皆さんに強く伝えたい、これからの時代を生き抜くための「7つの羅針盤」を共有しましょう。
1. 「課題発見力」- "Why"を深く問う力
言われたことを120%のクオリティでこなす「オペレーター」は、いずれAIに代替されます。皆さんに求められるのは、常に「そもそも、なぜこれをやるのか?(Why)」という本質的な問いを立てる力です。
目の前の顧客ですら気づいていない、潜在的な課題(ペイン)を、鋭い観察眼と共感力をもって発見する。
外部の優秀なコンサルタントは、まず間違いなくこの能力に長けています。
彼らがどのようにクライアントにヒアリングし、課題を構造化し、本質を炙り出していくのか。
その思考プロセスを盗んでください。
優秀なデザイナーは、コードを一行も書く前に、ユーザーの課題を理解するために膨大な時間を費やすのです。
2. 「越境するコミュニケーション力」- 翻訳家であれ
新規事業は、異なる専門性を持つ人々の化学反応から生まれます。
エンジニアの言語、デザイナーの言語、マーケターの言語、そして経営層の言語。
これらは全く異なります。これからの価値ある人材とは、この「異文化」の間に立ち、双方の意図を正確に「翻訳」し、プロジェクトを前進させるハブとなれる人です。
外部のPMは、まさにこの「翻訳家」としての役割を見事にこなします。
彼らがどのように会議をファシリテートし、対立を解消し、チームを一つの方向に向かわせるのか。
そのコミュニケーション術のすべてが、皆さんへの学びとなるでしょう。
3. 「高速仮説検証(リーン)力」- 小さく、賢く失敗する勇気
日本の大企業が陥りがちなのは、完璧な計画を立てることに時間をかけすぎ、市場に出す頃には手遅れになっているというパターンです。
外部のプロは、壮大な計画書よりも、まず市場に問いを投げかけることを優先します。
MVP(Minimum Viable Product:顧客に価値を提供できる最小限の製品)を驚くべきスピードで作り、顧客の反応を見て、高速で改善のサイクルを回す。
またGoogle社の話にはなりますが、会社の精神は「Launch and Iterate(まずリリースして、反復せよ)」です。
一度の壮大な失敗より、百回の小さな学びある失敗の方が、はるかに価値がある。このマインドセットを、ぜひ彼らから学んでください。
4. 「PLを読む力」- ビジネスという"共通言語"の習得
自分が担当する仕事が、最終的に事業のPL(損益計算書)のどこに、どのようなインパクトを与えるのか。
この視点を持つことが、プロフェッショナルへの第一歩です。
コスト意識、費用対効果(ROI)、顧客獲得コスト(CAC)、顧客生涯価値(LTV)。これらはビジネスの世界の共通言語です。
かつて私がいた会社では、エンジニアでさえ「その新機能は、どれだけの収益インパクトがあるのか」を問われます。
外部のプロは、常にPLを意識して動いています。彼らの視点をインストールすることで、あなたの仕事の価値は飛躍的に高まるでしょう。
5. 「専門性の"タグ"」- "T型人材"を超え、"π型人材"へ
一つの深い専門性(I)と、それを他の領域と繋ぐための幅広い知識(T)を併せ持つ「T型人材」の重要性が叫ばれて久しいですが、これからはもう一歩先が求められます。
それは、二つ以上の専門性を持ち、それらを掛け合わせることで代替不可能な価値を生み出す「π(パイ)型人材」です。
例えば、「データ分析」×「UXデザイン」や、「エンジニアリング」×「マーケティング」といった組み合わせです。
自分の専門領域を確立した上で、次にどの専門性を身につけるべきか。常に自己をアップデートし、自分だけのユニークな価値を創造してください。
6. 「外部ネットワーク構築力」- 社外に"師"と"仲間"を持つ
あなたの世界は、会社の壁の内側だけで完結してはいけません。
社外のプロフェッショナルが集う勉強会やコミュニティに積極的に参加し、自分とは異なる視点や最新の知識を常にインプットし続けてください。
会社の看板がなくても個人として付き合える人脈、困ったときに相談できる社外の「師」を持つこと。
これが、変化の激しい時代における最強のセーフティネットになります。
外部から来たプロフェッショナルは、まさにそのネットワークの塊です。
彼らと個人的な関係を築くことは、あなたのキャリアにとって計り知れない資産となるでしょう。
7. 「アンラーニング(学びほぐし)力」- 昨日の成功体験を捨てる勇気
最後に、最も重要かつ最も難しいのが、このアンラーニングの力です。
過去の成功体験や、かつては正しかった知識にしがみつくことなく、自らそれを潔く捨て去り、OSを常にアップデートし続ける。
変化に対応する唯一の方法は、自らが変化し続けることです。
成功体験は、時に未来への足枷となります。
常に自分を疑い、学びほぐし、新しい知識を吸収する謙虚さと柔軟性。これこそが、未来を生き抜くための究極のスキルなのです。
第3部 君たちは未来の「事業家」だ - 外資系企業が求める人材と日本企業の可能性 -
ここまで、皆さんが学ぶべき7つの羅針盤についてお話ししてきました。しかし、これらは単なる個別のスキルセットではありません。これらすべてを内包する、これからの時代を生き抜くための「マインドセット」そのものなのです。
Google社が求める「スマート・クリエイティブ」との合致
よく聞く話ではありますが、Google社が理想とし、探し求めている人材像を、「スマート・クリエイティブ(Smart Creative)」と呼んでるそうです。
深い専門性を持ちながら、ビジネス全体を理解し、好奇心旺盛で、常に学び続けます。
そして、自律的に行動し、データを駆使して周囲を巻き込み、大きなインパクトを生み出すことに情熱を燃やす人材像になります。
もうお分かりでしょう。
私が先ほど挙げた7つのスキルは、まさにこの「スマート・クリエイティブ」の構成要素そのものなのです。
自ら課題を発見し(1)、多様な人々を繋ぎ(2)、高速で仮説を検証し(3)、ビジネスの観点を持ち(4)、複数の専門性を掛け合わせ(5)、社内外から学び(6)、過去に固執しない(7)。
こうした人材こそ、Google社にかぎらず、最大手の企業が世界中から探し求めている逸材であり、これからの日本企業を再び成長軌道に乗せることのできる人材に他なりません。
Google社の目標管理手法であるOKR(Objectives and Key Results)がなぜ強力に機能するのか。
それは、社員一人ひとりがスマート・クリエイティブとして、会社の挑戦的な目標(Objectives)と、自らの具体的な貢献(Key Results)を主体的に結びつけ、自律駆動で動く文化があるからと、Googleの人材開発にいたピヨートル氏に著書にも記載されてます。
7つのスキルを身につけた皆さんは、まさにこのOKRを体現できる「事業家」としてのポテンシャルを秘めているのです。
アウトソーシング時代を「最高の学びの場」に変える
これからの皆さんのキャリアは、会社に所属しながらも、常に「自分株式会社の代表取締役」として、あるいは「外部のプロフェッショナル」として働くという意識を持つことが極めて重要になります。
「自分の市場価値は何か」「現在の報酬に見合うバリューを出せているか」を常に自問自答してください。
その観点に立てば、外部のコンサルタントや専門家と共に働く機会は、彼らの超一流の仕事術を「盗む」ための、またとないチャンスです。
彼らがどのようにクライアントの懐に入り込み、複雑な課題をシンプルに整理し、人を動かし、結果を出していくのか。
その一挙手一投足を観察し、模倣し、自分なりに昇華させていく。
これは、どんな高額な研修よりも実践的で価値のある学びです。
会社がお金を払って、皆さんのために最高の家庭教師を雇ってくれている。そう捉えることだってできるのです。
未来は、君たちの手の中にある
日本の大企業が外部人材の活用を加速させている。
この事実は、旧来の日本型雇用システムの限界を示唆していると同時に、変化に適応しようと挑戦する、企業のポジティブな意志の表れでもあります。
そして何より、意欲ある若手にとっては、会社のプラットフォームとリソースを最大限に活用し、社内外のプロフェッショナルから貪欲に学び、自らを「事業家」へと鍛え上げる絶好の機会が到来したことを意味します。
悲観する必要は何もありません。
会社という安全地帯から一歩踏み出し、7つの羅針盤を胸に、学びの航海に出てください。そうすれば、数年後、皆さんは会社の内部から、あるいは独立したプロフェッショナルとして、日本のイノベーションを再燃させる中心的存在になっているはずです。
未来は誰かが与えてくれるものではありません。
君たち自身の手で、創り上げていくものです。健闘を祈ります。



