デジタルマーケティング「戦略」という言葉で執筆しているマーケッターの言葉遊びに気を付けて下さい
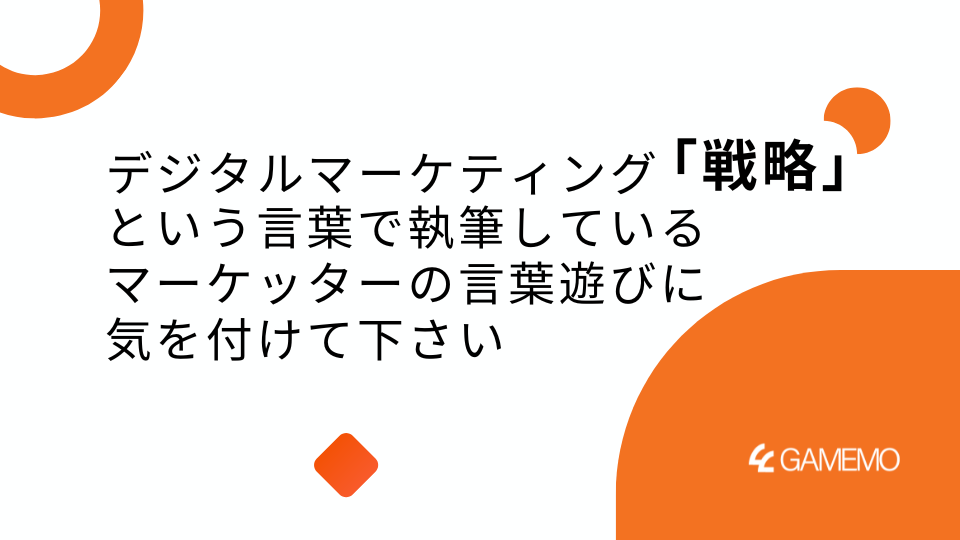
「デジタルマーケティング戦略」という言葉に惑わされていませんか?本質を知らず戦術を戦略と呼ぶ“なんちゃってマーケッター”は業界に多いもの。目的と手段を区別し、基盤を理解することこそ、若い世代が真に成長する鍵です。
最近、やたらと耳にする「デジタルマーケティング戦略」という言葉。
セミナー資料やSNSの投稿では必ずと言っていいほど登場する。
だが、その中身を見れば、戦略どころか単なる戦術の寄せ集め。
「Instagramを活用した戦略」「SEO戦略で上位表示」……。
恐縮ですが、それ、ただの手段ですよ。
戦略の定義も知らずに“戦略家”を名乗る人間がマーケ業界には多すぎる。
軍事の世界で「戦略(strategy)」とは、国家や軍隊が「最終的に何を成し遂げるのか」を定めるものだ。
例えば「戦争に勝つ」「敵国を降伏させる」といった大目的である。
逆に「夜襲をかける」「橋を爆破する」といったのは戦術(tactics)でしかない。
言葉を取り違えれば、戦場では命が失われる。
ビジネスの現場でも同じこと、戦略を知らない者がいくら戦術を繰り返しても、結果は出ない。
戦略を「かっこいい響き」にしているだけ
それなのに、本を書いたり、資料作成の好きなマーケッターと呼ばれる人の中には「戦略」という言葉を口にした瞬間、自分が高尚な思考をしている気になっている人がいる。
戦略という響きに酔いしれて、「俺は上流工程をやっているんだ」と悦に入る。
だが実際は、「SNSにリールを投稿しましょう」と言っているだけ。
戦争で例えれば、「敵が攻めてきたら頑張って守りましょう」と言っているのと同じ。
小学生の作文レベルとしか思わずにはいられないと思うのは私だけではないはず。
もし本当に戦略を語りたいなら、「何のために勝つのか」「勝利とはどういう状態か」を定義せよ。
それがない「戦略」は、ただの戦術カタログにすぎない。
作戦も兵站も知らない似非マーケッター
軍事には戦略・戦術に加えて「作戦(operation)」と「兵站(logistics)」がある。
作戦とは複数の戦術を束ねた行動計画、兵站は戦いを支える補給と基盤だ。
マーケティングに置き換えれば、作戦は「新商品発売に合わせた半年間のキャンペーン設計」、兵站は「予算配分やデータ基盤の整備」にあたる。
だが、なんちゃってマーケッターの頭には「作戦」も「兵站」も存在しない。
あるのは「戦略」と呼びたい小手先の施策だけ。
兵站を軽視した軍隊が全滅するように、基盤を整えない企業はどれだけSNSを更新しても勝てない。
だが彼らはそこには目を向けない。
理由は単純、「戦略」と言った方がカッコいいからだ。
太平洋戦争から学べ
歴史を見れば、戦略を誤った国の末路は明らかだ。
日本の太平洋戦争は「短期間でアメリカを屈服させる」という非現実的な戦略を掲げた。
その結果、現場の戦術がどれほど巧妙でも、戦争そのものが成立しなかった。
デジタルマーケティングで「戦略」と呼んでいるものの多くも、これと同じだ。
非現実的な目標を掲げ、戦術の断片をつなぎ合わせて悦に入る。
数千年前より、敗北の構図はいつも一緒だ。
新卒や学生への忠告
これからマーケティング業界を目指す学生や新卒社会人に言わせて頂く。
「戦略」という言葉の響きに酔わされるな。
戦略は目的であり、戦術は手段だ。
作戦はその橋渡しで、兵站は土台だ。
これを理解できなければ、一生「施策屋」で終わる。
「戦略的SNS投稿」と言い張る先輩を見かけたら心の中でおおいに笑えばいい。
「それはただの投稿計画でしょ?」と。
戦略を語る資格があるのは、目的を定義できる者だけだ。
マーケティングを学ぶなら、軍事史を読むことをおすすめする。
クラウゼヴィッツは難解でも、「戦略とは政治目的を実現する手段」という核心を突いている。
戦争とビジネスは違うが、人間が集団で目的を達成しようとする構造は同じだ。
最後にもう一度言う。
言葉の定義も理解せずに、戦略というキーワーが気持ちよくて、ただ使うだけのなんちゃってマーケッターに騙されるな。
戦術を戦略と呼ぶのは、兵站を忘れて突撃する愚かな軍隊と同じだ。
結末はいつも敗北である。



