JPYCなど、日本のステーブルコイン乱立時代、本当に必要なのか? 海外との温度差から見る「安定」の行方
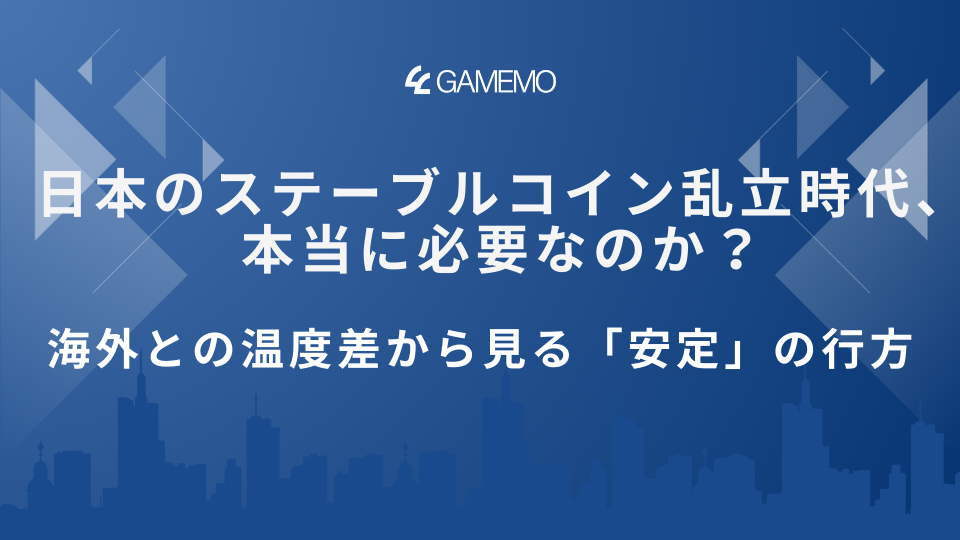
日本の金融業界で乱立するステーブルコイン。JPYC、ゆうちょ銀行、三菱UFJ信託、SBIなどが参入する一方、海外ではUSDCやUSDTが主流です。本記事では、複数のデジタル円がもたらす流動性分断や「ウォレットの壁」などの課題、海外との温度差を徹底検証し、日本市場の未来と真の安定の条件を探ります。
日本の金融業界は今、空前のステーブルコインブームに沸いている。
JPYC、ゆうちょ銀行、三菱UFJ信託銀行、SBIホールディングスなど、名だたる企業が参入を表明し、それぞれが独自の「デジタル円」を掲げている。
しかし、この熱狂の裏で、Web3の最前線にいる海外ユーザーや、すでにUSDCやUSDTを使いこなしている日本の暗号資産ユーザーからは、冷ややかな視線が向けられている。
「なぜ複数のステーブルコインが必要なのか?」
「結局、ウォレットの壁は解決しないのでは?」
「借りて投資なんて、一般には怖すぎる」
本稿は、こうしたWeb3コミュニティからの疑問と不安に正面から向き合い、日本のステーブルコイン市場の現状と課題を、海外との温度差を交えながら、一人の記者の目線で徹底的に検証する。
1. 「複数のステーブルコイン」という“不安定な”状況
Web3界隈のユーザーから最も多く聞かれる疑問は、この「複数のステーブルコイン」という状況自体が不安定ではないか、という点だ。
海外では、USDCやUSDTといったごく少数のステーブルコインが市場の大部分を占め、流動性が集中している。
これにより、DeFi(分散型金融)プロトコルや取引所での取引が効率的に行われている。
一方で、日本の現状は異なる。
- ユースケースの分散: ゆうちょ銀行は決済、三菱UFJ信託銀行はデジタル証券、JPYCはDeFiと、それぞれのステーブルコインが異なるユースケースを想定している。これは一見、戦略的だが、裏を返せば、「どこでどのステーブルコインが使えるか分からない」というユーザーの混乱を招く。
- 流動性の分断: 複数のステーブルコインが並存すると、市場全体の流動性が分断される。例えば、A社のステーブルコインはレンディングに使えるが、B社のコインは使えないといった状況が生まれる。これは、DeFiの最も重要な要素である「流動性のプール」を細分化させ、結果的にユーザーの利回りを低下させる要因となりうる。
海外のWeb3コミュニティは、「統一された規格と高い流動性」こそが、ステーブルコインの安定性を保証する上で最も重要だと考えている。
日本の企業がそれぞれ独自規格のステーブルコインを発行することは、この思想とは真逆の動きであり、Web3ネイティブなユーザーにとっては違和感しかないのだ。
2. ステーブルコインを借りて投資する、という「一般にポジティブではない」提案
日本のSNSやメディアでは、「ステーブルコインを借りて暗号資産に投資する」という運用方法が、あたかも安全な投資手法のように紹介されることがある。
しかし、これは一般ユーザーに大きなリスクを負わせる可能性がある。
- 担保割れのリスク: ETHやBTCを担保にステーブルコインを借りる手法は、担保資産の価格が下落すると、強制的に清算される「担保割れ」のリスクを常に伴う。特に、市場の急落時には、あっという間に資産が失われる可能性がある。
- 過剰担保の要求: 多くのDeFiプロトコルは、借り入れ額の1.5倍から2倍以上の担保を要求する過剰担保の仕組みを採用している。つまり、100万円借りるために200万円の資産が必要となり、一般的な銀行融資とは全く異なる概念だ。
海外のWeb3ユーザーは、こうしたレバレッジ運用を自己責任で行うことに慣れている。しかし、日本の一般ユーザーは、銀行の融資やカードローンといった「信用」に基づく借入に慣れており、「担保を失う」という概念には非常に大きな抵抗がある。この温度差を無視して、安易に「ステーブルコインを借りる」ことを推奨する記事は、無責任と言わざるを得ない。
3. 海外との温度差:なぜ日本はガラパゴス化するのか?
日本と海外のステーブルコイン市場における最大の温度差は、「規制とイノベーションのバランス」にある。
- 日本の規制先行型アプローチ: 日本政府は、資金決済法改正という形で、世界に先駆けてステーブルコインを法的に定義し、規制の枠組みを整備した。これは、消費者保護の観点からは評価できるが、同時に、革新的な技術やビジネスモデルの発展を阻害する側面もある。各社は、規制の枠内で動かざるを得ず、結果として「パーミッション型」で中央集権的なステーブルコインが主流になりつつある。
- 海外のイノベーション優先型アプローチ: 米国では、規制当局がステーブルコインをどう扱うかについて、まだ明確な結論が出ていない。しかし、このグレーゾーンが逆に、USDCやUSDTのような巨大なステーブルコインが、DeFiやWeb3の世界で爆発的に普及する土壌となった。彼らは、まず市場を創出し、その後に法規制を整えるというアプローチをとっている。
このアプローチの違いが、日本のステーブルコインが「既存の金融システムの延長線上」にある閉鎖的なものとなり、海外のステーブルコインが「オープンなグローバルインフラ」として成長した理由だ。
4. 記者の提言:日本が目指すべき「真の安定」とは
このままでは、日本のステーブルコイン市場は、Web3界隈とは完全に切り離された「ガラパゴス」な市場になりかねない。
真の安定と普及を実現するためには、以下の三つの課題に取り組む必要がある。
(1)共通規格と相互運用性の確保
各社が発行する日本円ステーブルコインは、特定の技術や発行体に依存しない共通のプロトコルと規格を採用すべきだ。
これにより、異なるステーブルコイン間でもシームレスな交換が可能になり、流動性の分断を防ぐことができる。
これは、日本の金融機関が協力して、「日本のデジタル円」としての統一したインフラを構築する、という意識を持つことから始まる。
(2)ユーザーに寄り添う教育とリスク開示
「ウォレットの壁」を隠すのではなく、その存在を正直に認め、それを乗り越えるための具体的なサポートをすべきだ。
- 「秘密鍵は銀行のキャッシュカードの暗証番号と同じくらい大切です」といった、一般ユーザーに伝わる言葉でリスクを説明する。
- 「ステーブルコインを借りて投資することには、担保を失うというリスクがあります。必ず余剰資金で行ってください」と、デメリットを明確に開示する。
こうした誠実な情報提供が、ユーザーの信頼を獲得する上で最も重要だ。
(3)オープンなWeb3エコシステムとの共存
日本のステーブルコインは、閉鎖的なシステムに留まるのではなく、パブリックブロックチェーン上のDeFiプロトコルとも連携すべきだ。
これにより、日本のユーザーは、国内で発行された安全なステーブルコインを使いながら、グローバルなWeb3エコシステムに参加できる。これは、日本の金融業界のイノベーションを加速させる上で不可欠なステップだ。
結論
日本のステーブルコイン市場は、金融機関の参入によって大きな可能性を秘めている。
しかし、Web3の最前線にいる人々の声に耳を傾けなければ、その可能性は、閉鎖的で非効率的な「ガラパゴス」な市場で終わってしまう。
真の安定とは、特定の企業や技術が支配するものではない。それは、統一された規格、高い流動性、そしてユーザーの信頼によって築かれる。日本のステーブルコインが、この道を歩むことができるか。その答えは、これから数年間の各社の戦略と行動にかかっている。



