JPYC EXがもたらす新時代の円建てステーブルコイン利用
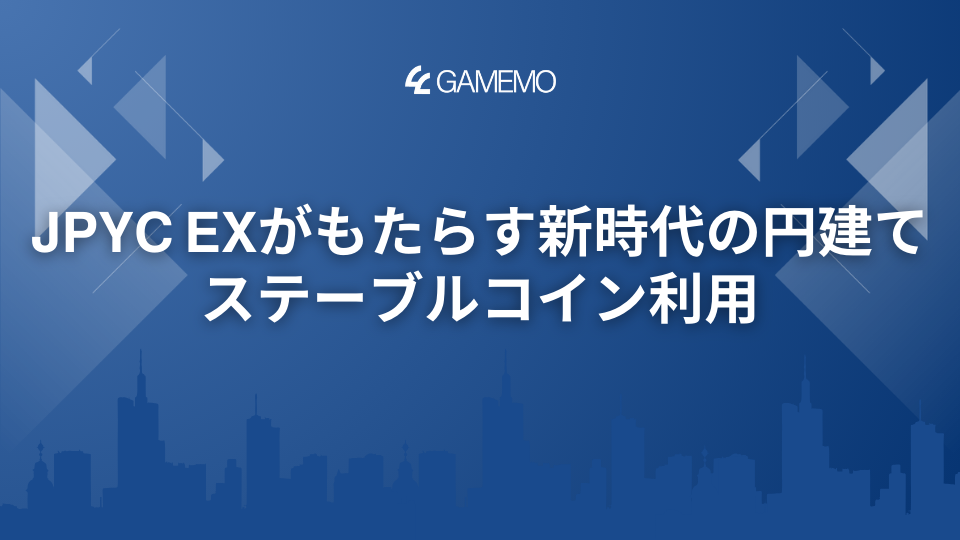
日本円連動ステーブルコイン「JPYC」の新サービス「JPYC EX」を徹底解説。発行・償還をブロックチェーン上で安全かつ透明に行える仕組み、ノンカストディ型ウォレットやKYC/AML対応による信頼性、手数料無料の利便性を紹介。国内外での利用拡大や金融インフラへの影響も解説します。
はじめに
近年、世界中で注目を集めている「ステーブルコイン」。
米ドルに連動するUSDT(テザー)やUSDC(USDコイン)は、暗号資産取引や送金の世界で既に不可欠な存在となっています。一方で、日本円に裏付けられたステーブルコインはまだ数が少なく、利用環境も十分とは言えません。
そうした中、JPYC株式会社が提供する日本円連動ステーブルコイン「JPYC」は、2025年秋に新しい専用サービス「JPYC EX」をリリースする予定です。
本記事では、このJPYC EXの仕組みや利用フロー、手数料体系、そして法制度上の特徴についてわかりやすく解説していきます。
JPYCとは? ── 円に連動する日本発ステーブルコイン
まずはJPYCそのものについて簡単に整理しておきましょう。
JPYCは「1JPYC=1円」と価値が連動する設計のステーブルコインです。裏付け資産としては日本円預金や国債が使われ、常に発行量以上の資産で担保されています。
米ドル連動型ステーブルコインに比べ、円建てのステーブルコインはまだ普及途上ですが、日本国内の決済や送金、さらにはブロックチェーンを使った新しいサービス展開において、その需要は確実に高まっています。
そんなJPYCの発行・償還をより効率的に、そして安全に行うために用意されたのが「JPYC EX」です。
JPYC EXとは? ── 発行と償還を専用に担う新基盤
JPYC EXは、JPYC株式会社が提供する「発行・償還専用のサービス」です。
これまでJPYCの利用は、主に取引所や外部のプラットフォームを通じて行われてきましたが、JPYC EXではユーザーが直接「発行(日本円を預け入れてJPYCを受け取る)」「償還(JPYCを返して日本円を受け取る)」を行うことができます。
主な特徴
- ブロックチェーン上で完結
JPYCの発行・償還は全てブロックチェーン上で処理されます。従来型のシステムと違い、取引履歴は改ざん不可能な形で公開され、透明性と信頼性が担保されます。
- ノンカストディ型ウォレット対応
JPYC EXは「ノンカストディ型」の仕組みを採用しています。つまり、ユーザーは自分のウォレットを使って直接発行・償還を行うことができ、運営側が資産を預かることはありません。この仕組みは、利用者にとって資産管理の自由度と安心感を高める重要なポイントです。
- KYC/AMLに対応
日本国内での金融規制に則り、JPYC EXでは本人確認(KYC)やマネーロンダリング対策(AML)が導入されます。これにより、安心して利用できる環境が整えられ、機関投資家や法人ユーザーにとっても利用しやすいサービス設計となっています。
- 手数料無料を実現
発行や償還にかかる手数料は原則無料。JPYCは裏付け資産である国債の利回り収益を活用することで、ユーザーから直接手数料を徴収せずに運営できるビジネスモデルを採用しています。
利用フローのイメージ
実際にユーザーがJPYC EXを使って発行・償還する流れを簡単に紹介します。
発行の流れ
- ユーザーがJPYC EXにアクセスし、本人確認を完了。
- 登録済みの銀行口座から日本円を入金。
- JPYC EXがその金額に応じたJPYCをブロックチェーン上で発行。
- 発行されたJPYCは、ユーザー自身のノンカストディウォレットに即時送付される。
償還の流れ
- ユーザーがJPYCをJPYC EXに送付。
- JPYC EXが受け取ったトークンをバーン(焼却)処理。
- 同額の日本円が登録口座に振り込まれる。
この仕組みにより、ユーザーは従来よりもスムーズかつ透明性の高い形でJPYCを扱うことができます。
JPYC EXのメリット ── 利用者と市場に与えるインパクト
JPYC EXの登場は、単なる利便性の向上にとどまらず、国内のブロックチェーン活用や円建て経済圏の拡大に大きなインパクトを与える可能性があります。
- 即時決済と手数料ゼロ
ネットワーク手数料(ガス代)は発生する場合があるものの、基本的に日本円⇄JPYCの交換は無料かつ即時。従来の銀行送金に比べ、時間やコストの大幅な削減が可能です。
- 企業の利用拡大
JPYCはすでに複数の企業と提携を進めていますが、JPYC EXによって導入のハードルが下がり、企業間決済や報酬支払いなど、法人ユースケースが広がることが期待されます。
- 透明性と安心感
ブロックチェーン上での処理に加え、KYC/AMLを徹底することで「安全かつ正規の手段で利用できる日本円ステーブルコイン」としての信頼性が高まります。
KYC/AMLの重要性 ── 日本市場に適した仕組み
暗号資産の分野では、マネーロンダリングやテロ資金供与といったリスクが常に指摘されています。特に日本市場では金融庁の規制が厳格であり、JPYC EXもこれに対応しています。
- 本人確認(KYC)により、利用者は必ず身元が特定される。
- AML対策として、取引のモニタリングや不正検知の仕組みを実装。
これにより、従来の「匿名性が高すぎてリスクがある」といった暗号資産利用の課題を解消し、健全な普及を後押しすることができます。
ノンカストディ型の強み ── ユーザー主導の資産管理
従来の取引所では、ユーザーの資産は取引所に一時的に預けられる「カストディ型」が一般的です。
しかし、過去には取引所の破綻や不正流用によって顧客資産が失われる事件も発生してきました。
JPYC EXが採用するノンカストディ型は、ユーザー自身がウォレットを管理し、その中に直接JPYCを受け取る仕組みです。これにより、第三者リスクを最小限に抑え、自分の資産を自分でコントロールできる点が大きな安心材料となります。
今後の展望 ── 日本発ステーブルコインの未来
JPYC株式会社は、JPYC EXのリリースを通じて、今後さらに発行規模を拡大し、3年以内に「発行残高1兆円規模」を目指すと公言しています。
また、国内利用にとどまらず、国際送金や海外取引の場面で「円建てステーブルコイン」が利用できるようになれば、日本円の国際的なプレゼンス向上にもつながるでしょう。
さらに、金融機関や決済事業者との連携が進めば、従来の銀行送金やカード決済と並ぶ新たな選択肢として広く普及する可能性があります。
まとめ
JPYC EXは、日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行と償還をシンプルかつ安全に行える新サービスです。
- ブロックチェーン上で完結する透明性
- ノンカストディ型ウォレット対応による安全性
- KYC/AMLによる信頼性
- 手数料無料&即時決済の利便性
これらの特徴は、個人ユーザーだけでなく企業や金融機関にとっても大きなメリットとなります。
円建てステーブルコインの活用が広がれば、日本の金融インフラやデジタル経済の発展に大きな役割を果たすでしょう。
今秋のリリースに向けて、JPYC EXがどのような形で市場に受け入れられるか、引き続き注目していく必要があります。



