デジタル赤字は本当に悪いのか?日本が世界で勝つための未来戦略
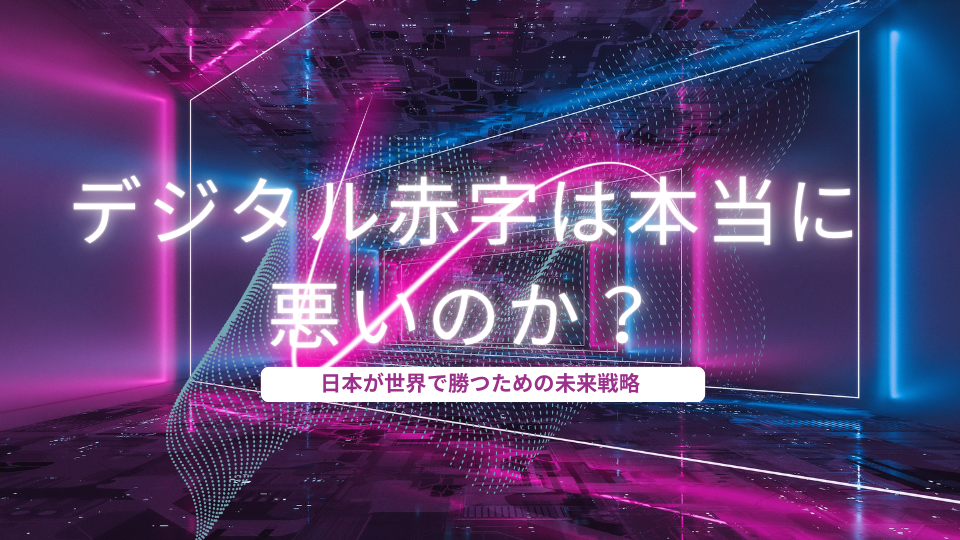
デジタル庁大臣・平将明氏が語る「見方」と「日本の強み」
「気がつけばスマホも、YouTubeも、Netflixも全部海外に持っていかれている」。
iPhone17の正式発表が間近に迫る中、SNS上では「デジタル赤字」に対する懸念の声が広がっている。デジタル赤字とは、OSやクラウドサービス、広告配信など、デジタル関連サービスの利用が増えるほど、日本のお金が海外に流出していくという構造的な問題だ。日本がDX化を進めれば進めるほど、この赤字は拡大していく。
では、日本のデジタル産業はどうなるのだろうか。この問題について、デジタル庁の大臣を務める平将明氏がで独自の視点を語った。
デジタル赤字の正体と、ゴリ押しでは勝てない現実
平氏によると、デジタル赤字の要因は多岐にわたる。OS(Microsoft、Apple)やアプリケーションのライセンス料、クラウドサービス(Amazon、Google)、ウェブ広告(Google、Meta)への支出が主なものだ。
しかし、平氏は「勝てないところに政府がゴリ押ししても勝てない」と現実を突きつける。iPhoneのようなハードウェアそのものではなく、その上で動くプラットフォームやサービスにこそ問題の本質があるという。
それでも、政府は手をこまねいているわけではない。例えば、政府のクラウドサービスにおいては、AmazonのAWSを使用している現状がある。これは、安全性や国際基準を満たす「ISMAP」の取得が困難であるためだが、国産クラウドサービスの「さくらインターネット」と連携して改善を試みている。また、政府自身が調査・研究を効率的に行えるよう、「ガバメント(政府)AI」の開発も進めており、外資系コンサルタントへの依存度を減らすことで、デジタル赤字の改善を図っている。
「レイヤー」ではなく「縦軸」で見ることの重要性
平氏は、デジタル赤字を悲観的に捉える必要はないと説く。半導体やクラウド、AIの大規模言語モデルといったレイヤーでは海外勢に太刀打ちできないかもしれないが、その上で動く「アプリケーション」や「コンテンツ」「ゲーム」といった分野では、日本は圧倒的に強いからだ。
「畑を借りる地代を払っても、その上で付加価値の高いものを作れば、収支は黒字になる。レイヤーごとの勝ち負けではなく、縦軸で見るべきだ」
これは、Web2.0の世界でも、Web3の世界でも同様だという。ブロックチェーン技術を基盤とするWeb3では、コンテンツの所有者の取り分が増える構造になっており、日本の強みであるコンテンツ力を最大限に活かすことができると見通しを語った。
アナログの価値を最大化するデジタル活用法
平氏は「日本はアナログが強い」という点を繰り返し強調した。観光、食、伝統文化など、世界が真似できないアナログの強みを持つ日本が、それらをタダや安価で提供している現状はもったいないという。
「なんでもデジタル化するのではなく、アナログの価値を最大化する方向にデジタルを活用すれば、日本は圧倒的に強い」。
これは、単にデジタル技術を導入するのではなく、日本の「強み」と「デジタル」を掛け合わせることで、新たな価値を創造するという考え方だ。例えば、日本の観光や伝統文化にデジタル技術を融合させることで、より魅力的な体験を提供し、収益を最大化できる。
また、スマホソフトウェア競争促進法(スマホ新法)の施行にも触れた。これは、AppleやGoogleの独占を規制し、国産アプリのスタートアップが競争環境の中で成長できるよう支援する法律だ。これにより、手数料が下がり、国産アプリが発展する土壌が整う。
編集長の所感:デジタル赤字をチャンスに変える日本の戦略
平将明氏の視点は、デジタル赤字を単なる「問題」としてではなく、「日本の強み」を再認識し、それを活かすための「チャンス」として捉えている点が非常に興味深かった。
マーケティングの観点から見ても、平氏が語る「レイヤーではなく縦軸で見る」という考え方は非常に重要だ。プラットフォームやインフラといった土台の競争に勝てないからといって、すべてを諦める必要はない。むしろ、その上で展開されるコンテンツやサービスといった「アセット」にこそ、日本の真の価値がある。
特に、Web3の「コンテンツ所有者の取り分が増える」という構造は、日本の強力なIP(知的財産)やクリエイティブ文化と相性が良い。これまではプラットフォーマーに利益を分配していたが、Web3を活用することで、クリエイターや企業が直接収益を得られるようになる。
今、日本が取るべき戦略は、海外のインフラに依存しつつも、そこでしか作れない「独自のアナログ体験」や、「質の高いコンテンツ」を創出することだ。これにより、デジタル赤字を相殺するどころか、大きな収益を生み出すことができるだろう。
「なんでもデジタル化」ではなく、アナログの価値を最大化するデジタル活用は、これからの日本企業のマーケティング戦略において、最も重要な視点になるだろう。



