消えゆく看板と、受け継がれる魂――ブランド売却の「不都合な真実」と再定義される価値
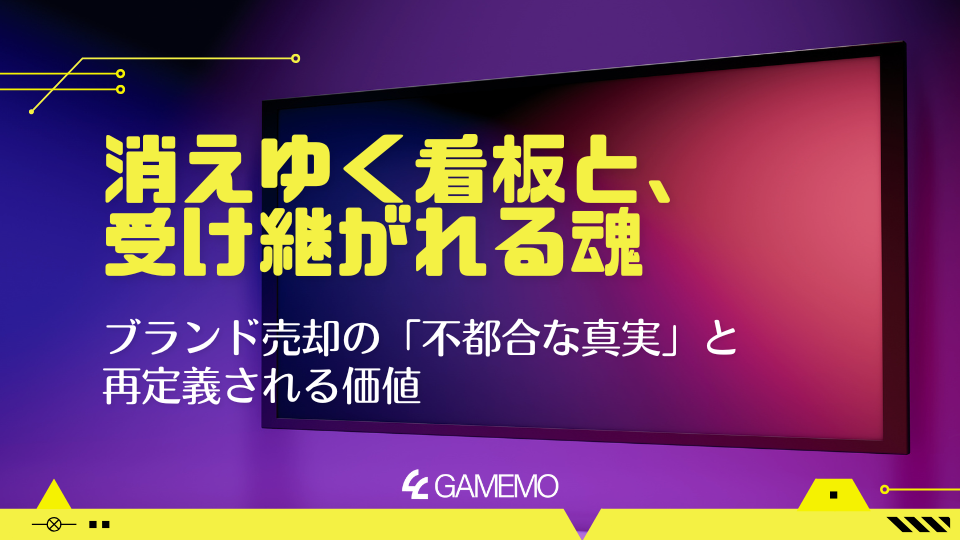
ソニー「BRAVIA」を起点に、REGZAやThinkPadなど日本企業のブランド売却が何を失わせたのかを考察。ロレアルや松屋のブランドM&Aと比較し、ブランドを「コスト」ではなく「資本」として活かす経営戦略の本質を解説する。ブランド価値、M&A、無形資産の視点から、企業が未来に何を残すべきかが分かる。
序論:BRAVIAという「生存」が突きつける問い
ソニーがテレビ事業「BRAVIA」を継続していることは、かつての「家電王国・日本」を知る者からすれば、ある種の驚きと安堵が入り混じる事象かもしれない。日立製作所がテレビの自社生産から撤退し、東芝の「REGZA」が中国・ハイセンスの傘下に入り、シャープが鴻海精密工業の軍門に降った激動の2000年代。
その中で、ソニーはBRAVIAを単なる「受像機」から、PlayStationや映画コンテンツと繋がる「エンターテインメントの窓口」へと再定義することで生き残りを図ってきた。
しかし、多くの日本企業が選択したのは、数十年かけて築き上げたブランドを切り売りし、当座のキャッシュとバランスシートの健全化を優先する「止血」の道であった。
LENOVOに渡ったIBM社THINKPADのPC事業、ハイセンスに渡ったREGZA。一時は経営難を救う「神の一手」に見えたこれらのブランド売却は、果たして数十年後の未来を見据えた真剣な経営判断だったのか。それとも、ブランドという「目に見えない無形資産」を数字でしか捉えられなくなった経営者の怠慢だったのか。
本稿では、ブランドを「消費者の信頼を蓄積する器」として捉え直し、日本の電機メーカーのブランド放棄と、欧米企業(ロレアル等)や新興勢(松屋等)のブランド収集という対照的な動きから、21世紀のブランド戦略の正体を暴いていく。
第一章:ブランド売却という名の「知的・文化的資産」の放棄
日本企業がブランドを売却する際、決まって使われる言葉がある。「選択と集中」だ。
不採算部門を切り離し、収益性の高いコア事業にリソースを集中させる。
これは経営学的には正論に見える。しかし、ブランドとは単なる部門の名称ではない。そこには、技術者のこだわり、消費者の愛着、そして「その名前があるからこそ成立する商流」という膨大なサンクコスト(埋没費用)が眠っている。
「REGZA」が証明したブランドの独立性
東芝からハイセンスに売却されたREGZAの事例は示唆に富んでいる。興味深いのは、ブランドが他社に渡った後も、REGZAは日本市場で強い存在感を放ち続けている点だ。
これは「東芝」という親会社の信用がなくても、商品そのものに宿る「画質へのこだわり」というブランド価値が消費者に根付いていたことを意味する。
しかし、ここで問うべきは「なぜその価値を、生みの親である日本企業が維持できなかったのか」という点だ。
ブランド売却は、一瞬の売却益と引き換えに、将来にわたって得られたはずの「顧客との接点(タッチポイント)」を永久に失うことを意味する。
ブランドの消失がもたらす「産業の空洞化」
PC事業(THINKPAD)をLENOVOに譲渡したIBMも同様だ。ブランドを貸与、あるいは売却することで、一般消費者の生活から自社のロゴが消えていく。これは単に製品が売れなくなる以上のマイナスをもたらす。それは、次世代を担う若者たちからの「認知」の消失だ。
数十年かけて築いたブランドを失うことは、その企業が「何者であるか」を語る言葉を失うことに等しい。ブランドを切り売りする経営は、家宝を売って食いつなぐ没落貴族の振る舞いに似ている。
第二章:ロレアルに見る「ブランド・コレクター」の哲学
ブランドを「負債」とみなして切り離す日本企業に対し、世界最大の化粧品メーカー・ロレアルは、ブランドを「増殖する資産」として買い集め続けている。
最近では、オーストラリア発の高級スキンケアブランド「Aesop(イソップ)」を約3400億円で買収したことが話題となった。
買収後の「魂」の保存
ロレアルの凄みは、買収したブランドを「ロレアル色」に染めないことにある。彼らは買収したブランドが持つ独自の世界観、文化、哲学を最大限に尊重し、バックエンド(サプライチェーンや研究開発)のみを自社の強力なリソースで支援する。
Aesopのような、エシカルでミニマルな哲学を持つブランドを、巨大資本であるロレアルが飲み込む。
一見すると矛盾するようだが、ロレアルは「ブランドの魂」に手をつけないことが、その経済的価値を最大化する唯一の方法であることを知っている。
ポートフォリオとしてのブランド
ロレアルにとって、ブランドとは「多様な価値観へのアクセス権」である。
自社でゼロからAesopのようなブランドを作るには数十年かかる。
ならば、その時間を金で買い、自社のポートフォリオ(資産一覧)に加える。
これはブランドを「消耗品」ではなく「投資対象」として見ている証拠だ。
第三章:松屋フーズの「六厘舎」買収が示す、日常ブランドの深化
異業種のように見えるが、牛丼の「松屋」がラーメンチェーン「六厘舎」を運営する松富士を買収した動きも、ブランドの本質を突いている。
「牛丼一本足」からの脱却と、ブランドの横展開
松屋は長年、牛丼(牛めし)というコモディティ化しやすい市場で戦ってきた。
しかし、原材料費の高騰や顧客層の固定化という課題に直面している。ここで彼らが選んだのは、自社でラーメン屋を始めることではなく、すでに圧倒的な「行列という信頼」を勝ち得ている「六厘舎」というブランドを手に入れることだった。
仕組みとブランドの補完関係
松屋が持つ巨大な物流網、店舗開発力、そしてセントラルキッチンのノウハウ。
これらを「六厘舎」という強いブランドに掛け合わせることで、ブランドの価値を毀損せずに規模を拡大できる。
これは、ブランドを「特定のファンを惹きつける磁石」として活用する、極めて現代的なM&A戦略だ。
第四章:ブランドを「コスト」と見るか「資本」と見るか
なぜ多くの、日本企業は、ロレアルや松屋のようにブランドを「使いこなす」ことができず、売却という選択に至るのか。
そこには、日本の会計慣行と経営教育の根深い問題がある。
無形資産を評価できない経営者
日本の経営者の多くは、工場や設備といった有形資産には投資するが、ブランドやデザイン、ソフトウェアといった無形資産の評価に疎い。
ブランド売却によって一時的に利益が出れば、株主への体裁は整う。
しかし、そのブランドが30年後に生み出したであろうキャッシュフローの総和を計算に入れている経営者は稀だ。
「一瞬の収益」の裏にある巨大な損失
ブランドを他社に渡すということは、そのブランドが持つ「信頼」という利息を他社に譲渡することに他ならない。
例えば、REGZAがハイセンス傘下でヒットを続けるたびに、かつての親会社は「自らが生み出した価値を、他社の利益のために使わせている」という屈辱的な現実に直面することになる。
これは、数十年かけて育てた苗木が実を結ぶ直前に、他人に根こそぎ売り払うような行為だ。
第五章:BRAVIAが残された意味――ソニーの「執念」を再考する
ここで冒頭のBRAVIAに戻る。ソニーがBRAVIAを手放さなかったのは、それが「ソニーという体験」の出口(インターフェース)だからだ。
ソニーは2010年代前半の苦境時、PC事業(VAIO)は売却したが、テレビ事業は分社化に留め、自社内に維持した。それは、テレビが消えれば、ソニーの映画も、音楽も、ゲームも、消費者のリビングに届く「最後の1メートル」を支配できなくなることを本能的に理解していたからだろう。
ブランドを維持することは、苦しい時に赤字を垂れ流すリスクを伴う。
しかし、それを乗り越えた先にしか、ブランドの「深化」はない。今のBRAVIAは、単なるテレビのブランドではなく、「ソニーの画質・音響技術の結晶」という高付加価値ブランドへと昇華された。
これは売却を選択した他社には決して到達できない領域である。
結論:ブランドの「死」と「再生」の境界線
ブランドを売却するビジネスの本当の意味。
それは、厳しい言い方をすれば「未来の創造を諦め、過去の遺産を現金化する幕引き」である。
一瞬の収益改善は、麻酔のようなものだ。
痛みを忘れさせてくれるが、病根(競争力の欠如)を治すものではない。一方で、ロレアルや松屋のように、他者のブランドを自社の血肉として取り込む企業は、ブランドを「時代に合わせて組み替えるレゴブロック」のように捉えている。
ブランドとは、数十年という時間をかけて醸成される「信頼の貯金」である。それを引き出す(売却する)のは簡単だが、一度空になった口座に再び信頼を貯めるには、また数十年の歳月が必要になる。
日本企業が今、真剣に考えるべきは、目先のEBITDA(償却前営業利益)の改善ではなく、「自社の名前が消えた世界で、自分たちは何によって記憶されたいのか」という根源的な問いである。
ブランドを売ることは、その企業の「魂」を切り売りすることに等しい。
BRAVIAが今もソニーのロゴを掲げて店頭に並んでいるという事実は、効率性だけでは語れない「企業のプライド」が、かろうじて日本の中にも生き残っていることを示している。
私たちはその背中から、ブランドという名の「果てしない責任」を学び直さなければならない。



