これからの広告データ分析:その「問い」は、事業の未来を創るか?【第2部】
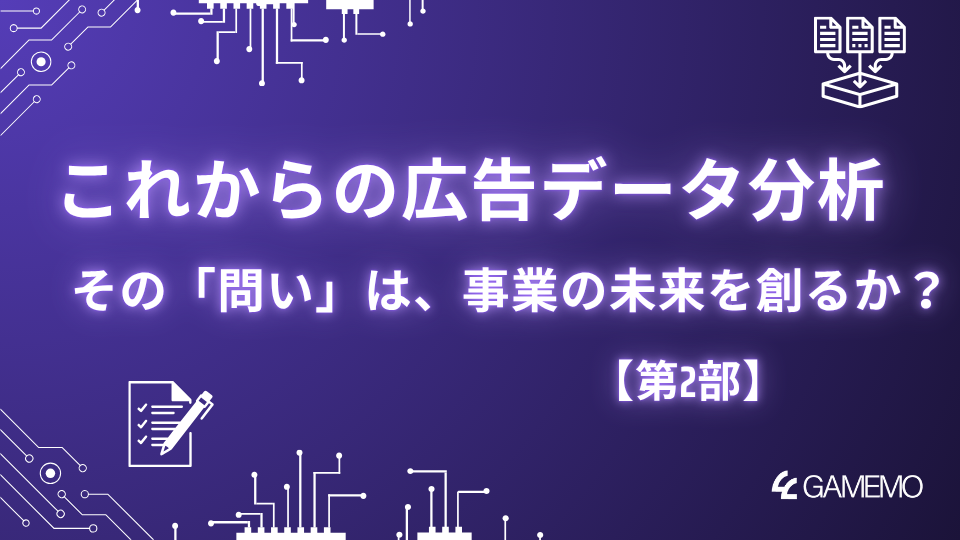
広告データ分析は“集める”から“問いを立てる”時代へ。マーケターとエンジニアが共に創る、目的ドリブンなデジタルマーケティングの新常識。データを事業成長へと導く実践知を3部構成で深掘りする必読連載です。【第2部】
第2部:沈黙するデータに「問い」を立てる技術 - 目的ドリブンなデータ基盤と分析アプローチ - (エンジニア視点)
第1部で述べたマーケターの苦悩。
これを「マーケターのスキル不足」や「リテラシーの問題」で片付けてしまうのは、あまりに短絡的だ。
彼らの苦しみの多くは、技術サイド、すなわちエンジニアが作り出すデータ基盤のあり方に起因している。
問題の本質はデータがないことではない。データに意味を与える「良い問い」が不在なこと、そして、その問いに迅速に答えられる環境が整備されていないことにある。
これからのエンジニアは、単なる「データ抽出屋」であってはならない。
マーケターのビジネスパートナーとして、沈黙するデータに生命を吹き込む「データアーキテクト」への進化が求められる。そのためのアプローチは、発想を180度転換することから始まる。
あるべき姿1:ビジネス要件から始めるデータ基盤設計
従来のデータ基盤構築は、「どんなツールを使うか」「どのデータを収集するか」といった技術的な視点から始まりがちだった。
しかし、このアプローチこそが「宝の持ち腐れ」を生む元凶だ。我々がまず始めるべきは、マーケターと共に「どんな意思決定を、どのくらいの頻度でしたいのか?」というビジネス要件を徹底的に突き詰めることだ。
例えば、「LTVを最大化する広告クリエイティブを特定し、週次で配信比率を最適化したい」という明確な「問い」があれば、エンジニアが構築すべき基盤は自ずと見えてくる。顧客IDをキーとして、広告媒体から得られる接触履歴、Webサイト上の行動履歴、基幹システムにある購買履歴、そしてCRM上の顧客属性データを統合管理できるデータウェアハウス(DWH)やCDPが不可欠となる。そして、週次の意思決定に耐えうるデータ更新頻度と処理速度が求められる、といった具合だ。ツール選定や技術選択は、このビジネス要件という名のゴールから逆算して初めて意味を持つ。
あるべき姿2:「使い捨て」ではない、再利用可能なデータマートの構築
マーケターからの場当たり的な抽出依頼にその都度対応するのは、非効率の極みだ。それは、毎回井戸から水を汲んでくるようなものだ。我々が構築すべきは、いつでも誰でも安全な水が飲める「水道」である。
具体的には、マーケターが頻繁に利用するであろうデータセットを、予め目的別に整理・加工した「データマート」として用意しておくのだ。
例えば、「日別の広告媒体別パフォーマンスマート」や「ユーザーセグメント別LTVマート」といったものだ。
これらのデータマートをBIツールに接続しておけば、マーケターはSQLを書けなくとも、自身の手でドラッグ&ドロップ操作で迅速に必要なデータを引き出し、分析を始めることができる。
これにより、マーケターは分析のスピードと自由を手に入れ、エンジニアは場当たり的な対応から解放され、より高度な分析モデルの開発やデータガバナンスの強化といった本質的な業務に集中できる。これは、両者にとって計り知れない価値を持つWin-Winの関係だ。
エンジニアの役割は、もはや依頼されたクエリを実行するオペレーターではない。
マーケターの漠然とした「問い」を具体的なデータ要件に翻訳し、それを実現するための最適なデータアーキテクチャを設計・提案する。時には、「その分析は、統計的に意味のある結論を導き出せますか?」と問いかけ、「こちらの顧客行動データと掛け合わせれば、もっと面白いインサイトが得られるかもしれません」と、ビジネスサイドに踏み込んだ提案をする。こうした対話を通じて、エンジニアは初めて、事業成長に貢献する真のパートナーとなれるのだ。
▼第3部はこちら




